残業までチャレンジしようとされているワーママのみなさん、毎日本当にお疲れさまです。
ワーママの残業問題、本当に難しいですよね。

このようなお悩みをもつ方も多いのではないでしょうか。
筆者もまさにそうで、ワーママになって3年目、仕事が終わらず月20時間の残業をしたことがありました。
本記事では、その経験をもとに、
- 実際、ワーママは残業してるの?
- どうやって育児・家庭と両立して残業までこなしてるの?
- 残業をした結果、どんな影響があったの?
といった点について、解説していきます。

✓4歳息子、0歳娘の育休中ママ
✓正社員フルタイムワーママ(残業月10~20時間)
✓両親遠方で頼れず
ワーママは残業をどのくらいしてる?
筆者の職場(総合職・一般職含む10名)における一例です。
| 残業30分未満(1日あたり) | 10人中7人 |
| 残業30分以上~2時間未満(1日あたり) | 10人中2人 |
| 残業2時間以上(1日あたり) | 10人中1人 |
やはり、ワーママは残業30分未満(概ね定時退社)の方が多い印象です。

ワーママ以外(男性社員等)は月40~50時間残業している方も珍しくない職場です。
しかし、「担当業務が多い」等の理由から、残業を30分~2時間程度する方もいました。
また、「祖父母と同居しており子どもたちの世話はお願いしている」という方は、日々2時間以上の残業をこなしていました。

※公的な機関による、ワーママの1ヶ月あたりの残業時間に関する調査は確認できませんでした。
どうやって育児・家庭と両立して残業をこなす?
筆者の実体験をご紹介します。

結論、しんどかったです。。。
1日のスケジュール
1日のざっくりとしたスケジュールはこんな感じです。
| 5時30分 | 起床、30分程で準備し出社 |
| 6時30分 | 勤務開始 |
| 17時30分 | 勤務終了、保育園お迎え |
| 18時30分 | 帰宅、夕食・入浴、家事全般 |
| 22時00分 | 子どもと一緒に寝落ち(就寝) |
こんな生活を2週間ほど続けていました。
- 朝食、お弁当、夕食の支度・片付け
- 洗濯物干し・片付け
- 子どもの明日の準備
こうした家事全般は、帰宅後~就寝までの時間帯で、子どもをみながら行っていました。
育児・家事を分担・省力化
夜の残業は子どもと過ごす時間を直接的に減らしてしまうため、早出出勤して業務時間を確保することとしました。
そのため保育園への子どもの送りは夫が、迎えは私が担当することとしました。


残業をするなら、夫は夜に、私は朝にすることにしました。
普段、家事は基本的に私が全てを担当しています。
しかし早朝に出社するため、子どもの朝の支度・布団の片づけは、夫にお願いすることとしました。
自分が担当する家事も、極力省力化しました。
- 洗濯:頻度を1日1回から2日に1回に落とす
- 掃除:平日は掃除をしない(やり方はこちらの記事にまとめています)
- 料理:オイシックスのおためしセット(送料無料)やコープのミールキット等を利用


ミールキットは、献立決め・買い物・調理という家事をすべてに大幅に減らしてくれるので本当に助かります…!
ちなみに、オイシックスのおためしセットは2回目の利用でした。
全てを一人でこなそうとすると倒れます。
頼れるものは頼りましょう…!
フルタイムワーママが月20時間残業した結果
月20時間の残業をしたことで、家族や仕事・自分自身にどのような影響があったのか、筆者の実体験をご紹介します。
子ども・家族へ影響
子どもに寂しい思いをさせないよう、保育園の送り迎えの時間は変えないなど工夫したつもりでした。

夜寝る前には、「明日起きたらママいる?」
朝は寝ぼけながら、泣きながら、「会社行かないで」
そんな言葉を毎日言われるようになり、この生活は子どもへの負担が大きく、継続できないと痛感しました。
仕事への影響
残業することで作業時間は確保できるようになりました。
しかし、寝不足感が強く集中力が落ち、時間あたりの仕事量は減少してしまいました。
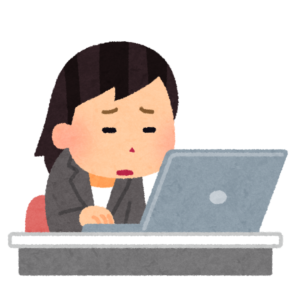
そのため、日常的な残業は非効率的だと感じました。
逆に、〆切のための短期的・集中的な残業であれば、有効だと思います。
自分自身への影響
疲れたらコーヒーや栄養ドリンクを飲み、なんとか体を動かしていた毎日。
自身への影響はないと思っていましたが、生理周期が大きく乱れるようになりました。
ここで初めて、「やはり、無理だったんだ」と気づきました。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本来、幼い子どもを育てながら働くというだけでも親子ともに物凄い負担なんです。
そんな中残業までこなすなんて、正直限界だと思います。
周囲からの目や、責任感でついつい無理をしてしまいがちな方もいるかと思います。(筆者もまさにその一人でした…)
しかしご自身と家族を第一に考え、どうしても残業が必要なのであれば上司に相談するなどして、なんとか乗り越えていきましょう…!
本記事が、読んでくださった方のお役に少しでも立てると嬉しいです。
最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました。
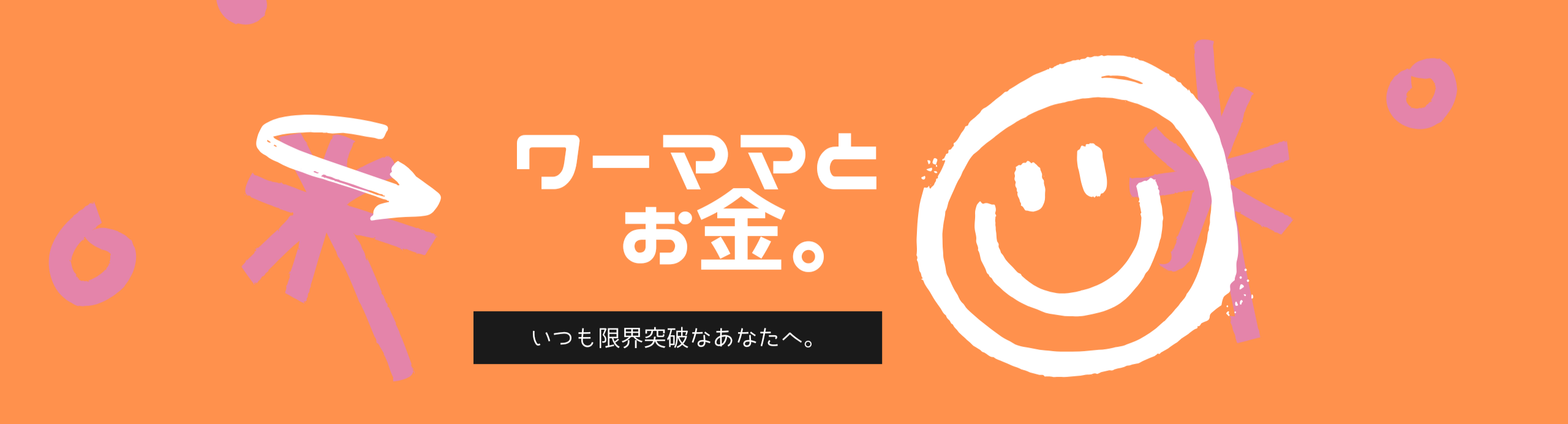




コメント