
このようなお悩みをもつ方も多いのではないでしょうか。私もそうでした。
- ワーママはいつから産休に入れるの?
- 実際問題、ワーママはいつから産休に入っているの?
- 早めに産休に入るには、どうすればいいの?
- 早めに産休に入ると職場から悪く思われない?
本記事では、実際に26週(妊娠7ヶ月)より有給休暇を取得し、32週より産休に入った私の実体験をもとに、こうした疑問について、回答していきます。

✓4歳息子、0歳娘の育休中ママ
✓正社員フルタイムワーママ(残業月10~20時間)
✓2人目の妊娠中とにかくしんどかった…
ワーママはいつから産休に入れるの?
労働基準法により、産休の開始期間は以下のとおり、(妊娠中の女性が請求した場合には、)産前6週間の産休取得が可能と定められています。
産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>
産後は8週間
女性を就業させることはできません。※ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。
実際問題、ワーママはいつ頃から産休に入っているの?
筆者の職場(総合職・一般職含む10名)における一例です。
| 産前6週より前に産休に入る | 10人中3人 |
| 産前6週に産休に入る | 10人中6人 |
| 産前6週より後に産休に入る | 10人中1人 |
やはり、労働基準法で定められている産前6週に産休に入る人が多いようです。
しかし、「体調が悪い」「有給が余っている」等の理由から、前倒して取得される方も一定数いる印象でした。
一方で、「仕事が好き」「キャリアアップしたい」等の理由から、臨月間近に産休に入るという方もいました。

なお、公的な機関による、産休開始時期の実態調査は確認されませんでした。
早めに産休に入るには、どうすればいいの?

では、早めに産休に入るためにはどういった手段が考えられるのでしょうか。
考えられる4つの方法をご紹介します。
有給休暇を取得する
1つ目は、当該年度の有給休暇の残日数を確認し、それらを産休取得前にまとめて取得する方法です。
有給休暇は一般的に2年間で消滅します。(労働基準法第115条より)
また復職時には、復職する年度の有給休暇が付与される会社も多いので、産休前にまとめて取得をおすすめします。

筆者は産休取得前に、余っていた22日間有給休暇を使い切りました。
産休取得までにできるかぎり有給休暇を減らさないため、筆者は以下の工夫をしました。

- 妊娠中の体調が悪い場合は、フレックス勤務や在宅勤務を活用し、有給休暇は取得しないようにした。
- 平日の妊婦健診は、有給休暇ではなく診査休暇(有給休暇)を取得して通院した。
- 子ども(一人目)の看病が必要な場合は、夫と公平に分担するようにし、有給休暇は取得しないようにした。
会社の制度を利用し休職する
2つ目は、会社の制度(福利厚生)を活用する方法です。
労働基準法により定められる産前休暇のの開始時期について、会社によっては、企業努力により前倒しで取得できる場合があります。
総務担当等に確認し、(前倒し可能であれば)それを活用するというのも一つの方法です。


筆者が勤め先では、産前8週間の産前休暇取得が可能でした。
ただし、前倒しの2週間は無給扱い・手当金対象外でした。
しかし、無給扱い・手当金対象外であっても、場合によっては手当金を受け取れる可能性があります。
それは、「予定日よりも早く出産した場合」です。
筆者は予定帝王切開であったため、予定日よりも2週間以上早い出産日となりました。
そのため、前倒した2週間も結果的に手当金が給付されることとなりました。

特に予定帝王切開の方は、確認・活用をおすすめします!
医師の診断書により休職する
3つ目は、医師の診断を受けて傷病休暇を取得する方法です。

妊婦健診等で、医師に心身の不調に伴い仕事の継続が困難な旨を伝えることで、医師の判断により診断書を書いてもらえる場合があります。
医師の診断書をもとに会社に相談することで、傷病休暇の取得ができます。
「診断書では、医師からの指摘事項が会社に正確につたわらない…」という方には、診断書のほかに、母性健康管理指導事項連絡カードの記入を医師にお願いするという方法もあります。※いずれも傷病休暇・傷病手当金の対象
「体調面で悩みがあり早く休みたい」という方は、まずは医師への相談をおすすめします。
急な入院や手術(帝王切開)の際には、保険に入っていると非常に助けられます。

筆者の友人は、切迫早産で妊娠中入院となり、保険金に非常に助けられたと言っていました。
筆者自身も、子どもが2人とも帝王切開で、保険にはとてもお世話になりました。
保険の無料相談サイトガーデンでは、保険の無料相談をすると、出産準備に嬉しい西松屋のギフト券や離乳食、アンパンマンのおもちゃ等、嬉しいプレゼントももらえます。
≫詳細情報や口コミ・実体験レポはこちらのページをご覧ください。

筆者は離乳食をいただきました。これを機に、保険の見直しおすすめです♡

欠勤する
- 有給休暇の残日数がない
- 会社独自での妊産婦休暇制度がない
- 医師に診断書を書いてもらえない
このような状況で産休を早めから取得する方法としては、欠勤するになります。
会社に相談をし認められれば、欠勤する形で早めに産前休暇を取得することが可能です。


金銭的な影響は大きいものの、母子の健康は何ものにも代えられませんよね。
早めに産休に入ると、職場に迷惑が掛かってしまうのでは?
ここまで、早めに産休に入る方法を見てきました。
様々な方法があり、制度的には産休に早く入ることは可能であったとしても、

と不安になり、躊躇してしまう方もいるのではないでしょうか。
そこで、26週(妊娠7ヶ月)より休暇を取得した筆者が実施した、「上司や同僚に悪く思われない・負担を軽減するための工夫」をご紹介します。

最終出勤日には、「本当にやりきったね」「元気な赤ちゃんを産んでね」と
温かく見送っていただけ、本当に感謝と一安心でした。
休暇に入るタイミングを考える
1つ目は、休暇に入るタイミングです。


筆者の場合、妊娠発覚時点で担当業務がひと段落する時期が決まっていたため、その時期を休職開始時期と決め、周囲にも伝えていました。
もちろん、長期にわたるプロジェクトでは、その完了を待っていては休職を開始できない場合もありますよね。
そういった場合には、「完了時期」ではなく、「(小さく)ひと区切りの時期」で、休職開始時期を決めるとよいと思います。
休職開始時期を早めに伝える
2つ目は、休職開始時期を伝えるタイミングです。
早めに伝えることで、上層部に自身の業務の引き継ぎ先や、人事配置を前広に検討してもらえるようにし、同僚等に負担が少なくなるよう心掛けました。

筆者は妊娠発覚時点で、休職開始時期を上司や同僚に伝えました。
早めから伝えることで、周囲に「○月から休むのは既定路線」と印象付けました。

「6月からが規定路線なのに、1か月余分に休むってこと?」
「俺たちはお前が休んだ分の業務を請け負ってるのに、お前は有給を全部消化かよ。。」
といったように、周囲からの印象が悪くなりかねませんので、要注意です。
引き継ぎは早めに丁寧にする
3つ目は、引き継ぎの仕方です。
あなたが休職に入り、いざ引き継ぎ書をもとに後任者が業務にあたろうとしたとき、
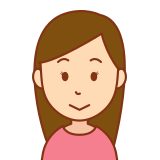
休職直前で引き継ぎされたから、確認できていないことが多い!

こんな業務があるなんて聞いてない!引き継ぎ不足じゃないか?
こんな風に思われてしまうのは嫌ですよね。
あなたの印象も悪くなりますし、後任者にも負担がかかってしまいます。


筆者は、休職開始の1ヵ月前から引き継ぎ書の作成を始め、周知会も実施しました。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
妊婦さんが10人いれば、その体調や職場・家庭環境も様々、十人十色です。

あの人は出産直前まで働いていたわよ

そんなに早く休みだすの?休みすぎじゃない?
もしかしたら、そんな心無い声があるかもしれませんが、
他人と比べず自分なりに、母子ともに健康に過ごせる最善を選択することが大切です。

この記事を読んでくださった方が、利用できる制度を活用して、希望する時期に気持ちよく産前休暇を取得できることを心から願っています。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
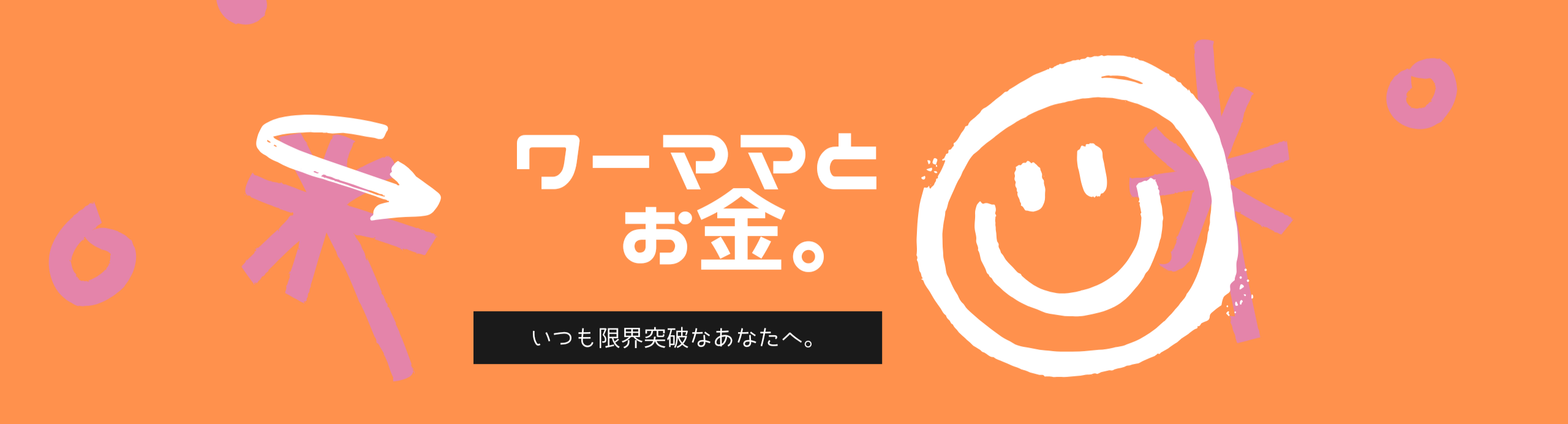





コメント